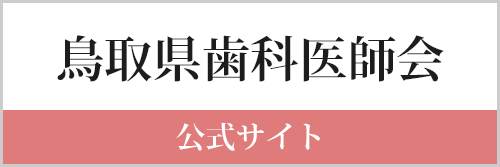今回は、むし歯がどうしてできるのかについて、少し詳しく説明したいと思います。
“どうしてむし歯ができるのか?”
このことを考えることには、とても重要な意義があります。
むし歯は、歯の病気の代表的なものですが、当院では、むし歯を“治療”することよりも、“予防”することの方が重要だと考えています。
病気の“予防”を考える上で、その原因、つまり“どうしてむし歯ができるのか?”が分かれば、その原因を取り除くことで、その病気の“予防”に繋げることができます。
“どうしてむし歯ができるのか?”
専門的な知識の無い方にたずねた時に多く聞かれる回答は、
「食べた後、歯を磨かないから」
「おやつなど、甘いものをたくさん食べているから」
ではないかと思います。
では、どうして
“食べた後、歯を磨かない”とむし歯になるのでしょう?
どうして
“おやつなど、甘いものをたくさん食べている”とむし歯になるのでしょう?
“食べた後、歯を磨く”のは、磨いて何をきれいに取り除いているのでしょうか?
これもたずねてみると、“食べかす”と答えられる方が少なくありません。
“食べかす”は、歯にとってどのような悪影響を与えているのでしょうか?
“甘いものをたくさん食べること”は、歯にとってどのような悪影響を与えているのでしょうか?
甘いものの“食べかす”が歯の周りにこびりついているからでしょうか?
これらの答えは、むし歯がどのようにしてできるのか、を少し詳しく考えていくと分かってくるかと思います。
古くから考えられているむし歯が発生する要因として、“細菌”、“糖分”、“歯の質”があります。これらに加えて“時間”も要因の一つとして考えられることもあります。
歯の表面にいる“細菌”が、その周囲にある“糖分”を分解して酸を産生し、その酸により歯が溶かされて穴が開いてしまうということです。同じ条件でも、“歯の質”が強いか弱いかによってむし歯になるかどうかも変わってきます。また、酸に晒される“時間”が長ければむし歯になるリスクは高くなります。
ですので、むし歯を予防するためには、これらの3つの要素を改善すればよいことになります。つまり、歯の表面にある“細菌”を取り除き、“細菌”への“糖分”の供給を減らし、“歯の質”を強くする、これらのことでむし歯になるリスクを減らすことができます。
前半にお話した、“食べた後、歯を磨かない”とむし歯になるのは、“食べかす”だけではなく、歯の表面に酸を作る“細菌”が長い時間存在するためであり、特に食べた後は、糖分も多く供給されているので、むし歯のリスクは高くなります。
また、“甘いものをたくさん食べること”は、その量よりも“時間”が重要で、たくさん食べることは、それだけ長い“時間”、“細菌”に“糖分”が供給され、多くの酸が長時間、歯の表面に作用することになります。
“どうしてむし歯ができるのか”について、一般に考えられている“歯を磨く”ことと“甘いもの”のことについて、説明しましたが、他にも“歯の質”もむし歯の成り立ちとむし歯の予防には大きく関与しています。
またの機会に、むし歯の成り立ちやむし歯の予防についても、もう少し詳しく説明したいと思います。
監修歯科医師

緑ヶ丘歯科クリニック
院長 田中秀司
【所属学会】
日本補綴歯科学会
日本ヘルスケア歯科学会
【経歴】
1969年2月1日 鳥取県鳥取市生まれ
1993年 広島大学歯学部 卒業
1993~1995年 広島大学歯学部附属病院 研修医
1995~1998年 広島大学大学院
1998~2000年 ペンシルバニア大学医学部 学位取得後 研究員
2000~2001年 広島大学歯学部附属病院 医員
2001~2005年 広島県呉共済病院 歯科 勤務
2005年 緑ヶ丘歯科クリニック 開院